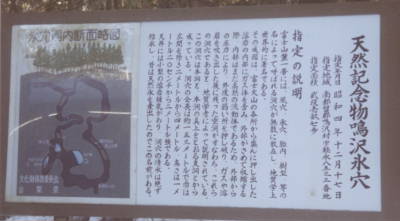 |  |
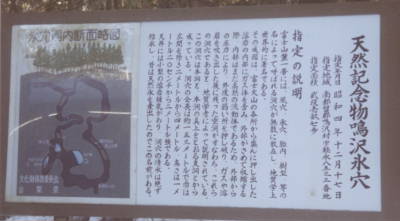 |  |
 |
||
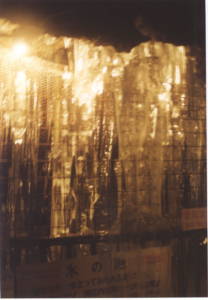 |  | 氷穴の中のようすです。溶岩からしみ出した富士山の伏流水が冷やされて氷になりました。1年中とけることはありません。 |
 |  |  |
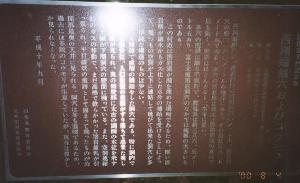
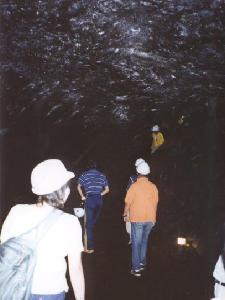 | 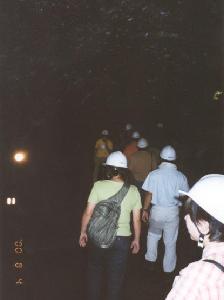 |
|
中にはいるときは、このようにヘルメットをかぶって入ります。 そうしないと天井が低いので頭をぶつけてしまったとき困る からです。中は迷路のようになっています。溶岩だなや、縄 状溶岩などめずらしいものが見られます。 | 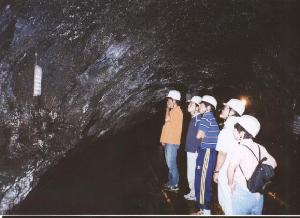 |
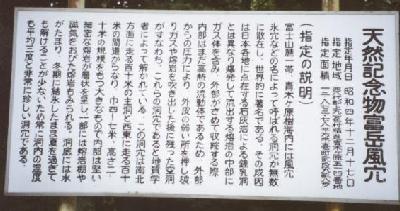
| 洞穴の名前 | 場所 |
| 富岳風穴 | 西八代郡上九一色村精進青木ヶ原 |
| 富士風穴 | 西八代郡上九一色村精進青木ヶ原 |
|
本栖風穴 (第1風穴・第2風穴) |
西八代郡上九一色村本栖石塚 |
| 西湖コウモリ穴 | 南都留郡足和田村青木ヶ原 |
| 竜宮洞穴 | 南都留郡足和田村青木ヶ原 |
| 鳴沢氷穴 | 南都留郡鳴沢村軽水 |
|
神座風穴 (蒲鉾穴・めがね穴) | 南都留郡鳴沢村神座 |
| 大室洞穴 | 南都留郡鳴沢村神座8536 |
| 雁の穴 | 富士吉田市上吉田雁の穴5605 |
 | 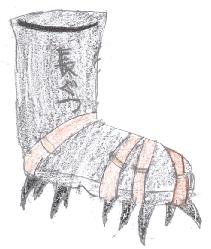 |